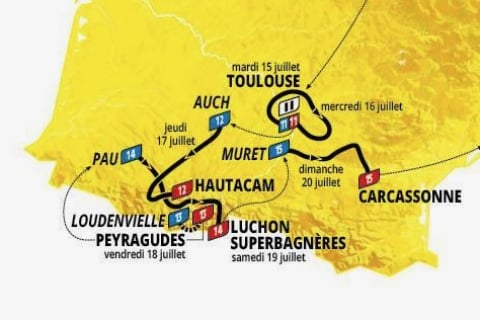2025年6月に行われた富士ヒルクライムに参戦するべく、緊急来日したトレックのジョン・バークCEO。「月に行くようなもの」と語った日本進出から30年以上が経ったいま、当時の苦労や渾身のバイクまで幅広く話を聞いた。

奥様とともに来日したジョン・バークCEO。特別に作られたMadone Gen8とともに photo:So Isobe
トレックの名を、知らないサイクリストはいないだろう。しかしその巨大ブランドを、今日の姿へと導いた人物についてはどうだろうか。この記事ではブランドではなく、その舵取りを担うCEO、ジョン・バークにスポットライトを当てたい。
1979年創業のトレック創業者ディックを父に持ち、1997年にCEOへ就任。その卓越した手腕で、当時数百億円規模だった同社を、売上3,000億円に迫るグローバルブランドへと成長させた立役者だ。今回、6月の富士ヒルクライムに合わせて来日した氏にインタビューする機会を得た。しかし本稿では、あえて氏の経営哲学といった核心に深く踏み込むことはせず、幅広いテーマについて一問一答形式で尋ねることに終始している。それはまだ見ぬ次なる機会に、より深い哲学を掘り下げるために。
異世界だった30年前の日本
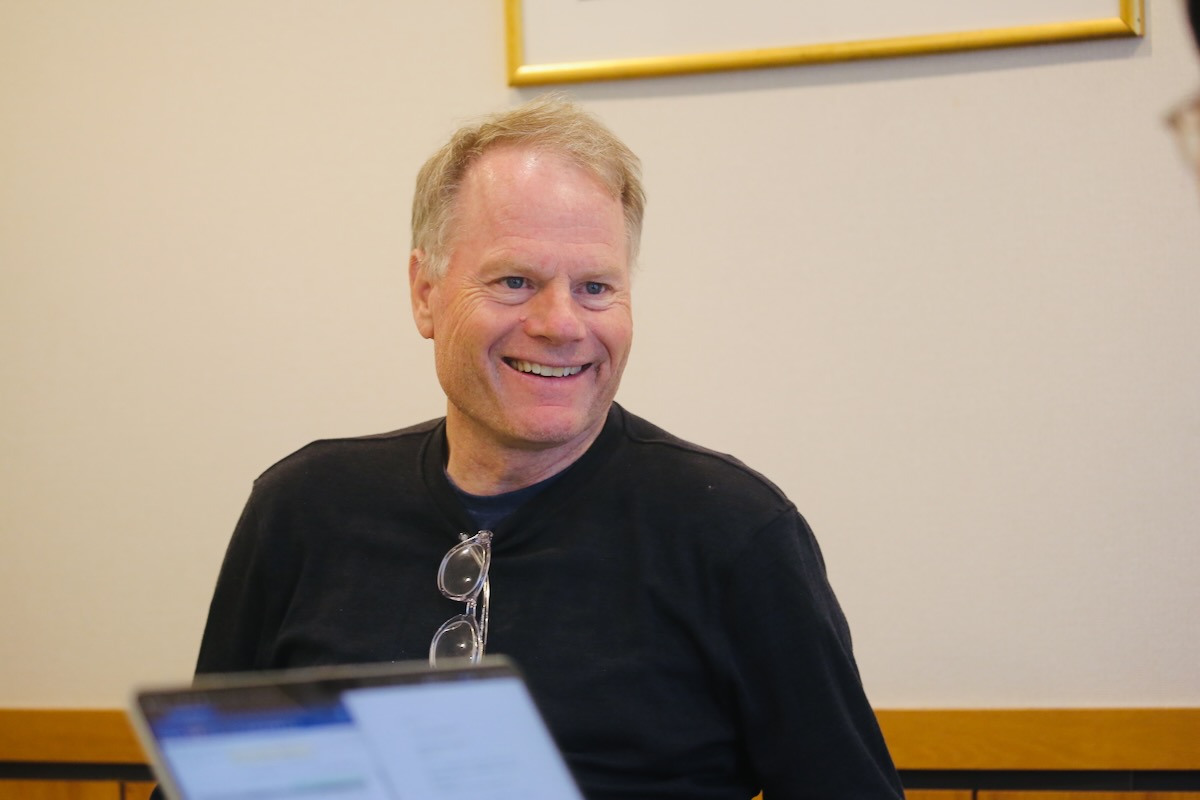
富士ヒル前日の土曜日にインタビューを実施。真剣に、ときおり笑いを混ぜながら話をしてくれた photo:So Isobe
──初めて日本に来たのはいつ頃ですか?
ジョン・バークCEO:CEOになる以前の、1988年のことだったと思います。当時は国際営業とマーケティングを担当しており、同年にスイスでヨーロッパ初の支店を立ち上げました。その後イギリス、そしてドイツへと拡大させ、そこで得た自信と共に日本市場にやってきました。
──バブルの絶頂期だった当時の日本はどのような感じでしたか。

「トレックをグローバルなステージへと押し上げたかった」 photo:So Isobe
──進出する上で、どんな障壁がありましたか。
特に言語の壁は高かったですね。でもそれはドイツやオランダでも直面したこと。それよりも当時はライバルがまだ少なかったので、僕らにはアドバンテージがありました。何よりも日本は美しい風景など自転車に適した国で、当時の日本には自転車に興味のある人たちがたくさんいました。
──内需だけでビジネスが回るアメリカを飛び出し、ヨーロッパや日本に進出したのはなぜですか。
私は小さい頃から歴史に興味があり、大きなビジョンによって偉業を達成する話が好きだったからです。それにトヨタやBMW、アップルをはじめ、素晴らしい企業はインターナショナルなマーケットを相手にしています。世界が一つになっていくなかで、トレックをグローバルなステージへと押し上げたかったのです。
パンデミックが生み出した好機
──CEOに就任してからいくつもの苦難があったと思いますが、近年ではコロナ禍などがありました。
パンデミックは、私がCEOとして体験した中でも、特に大きな試練の一つでした。2020年4月にコロナウイルスが世界を襲い、空輸や船便が止まり、物流が完全にシャットダウンしました。これは未曾有の大惨事となると思いました。しかし3週間が経ち、人々は屋外でのエクササイズを求め、自転車店には外にまで続く長蛇の列が並んでいました。
3週間の危機が、その後2年間に及ぶ自転車ブームを作り出したのです。ビジネスという名の旅路には、山もあれば谷がつきものです。

長い期間トレックファミリーの一員だった別府史之さんと久々に旧交を温めた photo:So Isobe
トレック最大のライバルは?
──同じアメリカのスペシャライズドや、近年はドイツのキャニオンも年々勢いを増しています。CEOに就任して30年になろうかというトレックの歴史で、最大のライバルはどこですか。
それは時代によって常に変わり続けてきました。初期はシュウィンで、やがてトレックvsスペシャライズドという構図が生まれました。でも重要なのはいかにインターナショナルな企業である続けるか。ヨーロッパや日本、中国への進出を躊躇い、消えていったブランドは数多くありましたからね。
──これまで悔しいと感じた、他社のバイクはありますか。
悔しいという見方はしていません。でも「これは面白いアイディアだ」と思うことはあります。見つけたら「これを見てみてよ」とデザイナーに送ることも。でもそれはバイクに限らず、車やアップル製品、エルメスのブランケットの時もあります。
──ブランケットからも、ですか。
そう。インスピレーションはどこにでも転がっていますからね。

他ブランドの出展ブースを視察するジョン・バーク氏 photo:So Isobe

トレック初のカーボンバイクとして発売されたトレック 5500 (c)トレックジャパン 
現在でもカルト的なファンのいるYバイク (c)トレックジャパン
──自社で印象に残っているバイクはどれでしょう。
1992年に発売したトレック 5500ですね。トレック最初のカーボン製のバイクです。他社が「カーボンなんて酷い素材で、すぐ壊れてしまう」と言うなか、私たちはNASA出身の科学者などを含む素晴らしいチームを作り、カーボンバイクのリーディングカンパニーとなりました。
他には1995年に発売したYバイクやカーボンのマウンテンバイク。Fuel EXや2008年のマドンなども大好きなバイクです。それに最新のマドンGen 8も胸を張って良いバイクだと言えますね。
「心から愛せるプロダクトか?」
──プロダクトの開発にはいま、どの程度関わってらっしゃるのですか。
私はエンジニアではありません。ですが、素晴らしい製品だと判断することはできます。チームが開発したプロダクトを隔週で確認し、自分に「これは心から愛せるプロダクトか?」と問いかけます。つまり私がトレックの最終関門なのです。
その際はチームに1つだけではなく、複数のデザイン候補を求めます。その方がクリエイティビティを生むからです。最悪なのは1つのデザインと結婚(固執)することですからね。

リドル・トレックのエースを担うマッズ・ピーダスン。開発においても重要な選手だという photo:RCS Sport
──マドンなどトレックのロードバイク開発には、男女ワールドチームであるリドル・トレックの選手たちのフィードバックが強く反映されていると思います。他ブランドのようにチームへ機材提供するのではなく、タイトルスポンサーになるメリットはどこにありますか。
良い質問ですね。自社でチームを所有しなければ、選手たちに本当の意味で機材をテストしてもらうことは難しいからです。我々は以前、それで大変な苦労をしました。選手たちと密にコミュニケーションを取ることで、初めて良いものを作ることができるのです。
例えばマッズ・ピーダスンがスプリントするラスト500mにおけるバイクの動きを、彼が言語化する様はまさにプロフェッショナルそのもの。トレックはエンジニアリングと真剣に向き合うため、真剣にバイクをテストする選手に、機材の限界を超える手伝いをしてもらっているのです。
──それは女子チームも同じですか。
そうです。我々は(2019年)に妊娠したエリザベス・ダイグナンと契約を結びました。妊娠したことによって前チームとの契約が打ち切られた彼女を中心に、チームを立ち上げました。劣悪な環境だった女子ロードレース界を変えるために。そして彼女は2021年にパリ〜ルーベ・ファムの初代優勝者となりました。その時の彼女の写真は、いまも会社に飾ってあります。

初代女子ルーベ覇者となったエリザベス・ダイグナン(イギリス)。 photo:A.S.O.
──女性用のサイズの小さなバイクの開発、調整は大変でしたか。
そうですね。細部までこだわると大変です。しかし我々は女子チームでのテストを通してそれを実現させ、あらゆるライダーにとって機能する製品をつくり続けようと励んでいます。
──本日はありがとうございました。明日は富士ヒルに参加されると聞きました。
いままでクレイジーな自転車イベントに参加してきましたが、9,000人以上のライダーが24kmの登り坂に挑む、こんなイベントは初めてです。素晴らしい体験になるに決まっています。

楽しみながらスバルラインを登ったジョン・バーク氏 photo:So Isobe
──軽量になったマドンでも、十分登れることを証明するために?
もちろんです。マドンは我々が開発した最高のオールラウンドバイクです。スプリントはもちろん、クラシックレースから登りまで対応できます。それは(リドル・トレックのクライマーである)チッコーネがレースで示している通り。クライミングバイクとしても素晴らしい性能を発揮することでしょう。
──最後に抽象的な質問にはなってしまいますが、トレックは今後、日本でどうなっていくのでしょうか。
我々のミッションはどの国であっても変わりません。素晴らしい製品を作り、ホスピタリティと共に届ける。そしてより多くの人々に自転車に乗ってもらいたい。私は日本が大好きです。人々は礼儀正しく、街は綺麗で管理が行き届いている。もしかしたら日本人ではない私たちの方が、この国がいかにスペシャルであるかを、より実感しているのかもしれません。

「素晴らしい製品を作り、ホスピタリティと共に届ける。そしてより多くの人々に自転車に乗ってもらいたい」 photo:So Isobe
text:Sotaro.Arakawa
photo:So Isobe

トレックの名を、知らないサイクリストはいないだろう。しかしその巨大ブランドを、今日の姿へと導いた人物についてはどうだろうか。この記事ではブランドではなく、その舵取りを担うCEO、ジョン・バークにスポットライトを当てたい。
1979年創業のトレック創業者ディックを父に持ち、1997年にCEOへ就任。その卓越した手腕で、当時数百億円規模だった同社を、売上3,000億円に迫るグローバルブランドへと成長させた立役者だ。今回、6月の富士ヒルクライムに合わせて来日した氏にインタビューする機会を得た。しかし本稿では、あえて氏の経営哲学といった核心に深く踏み込むことはせず、幅広いテーマについて一問一答形式で尋ねることに終始している。それはまだ見ぬ次なる機会に、より深い哲学を掘り下げるために。
異世界だった30年前の日本
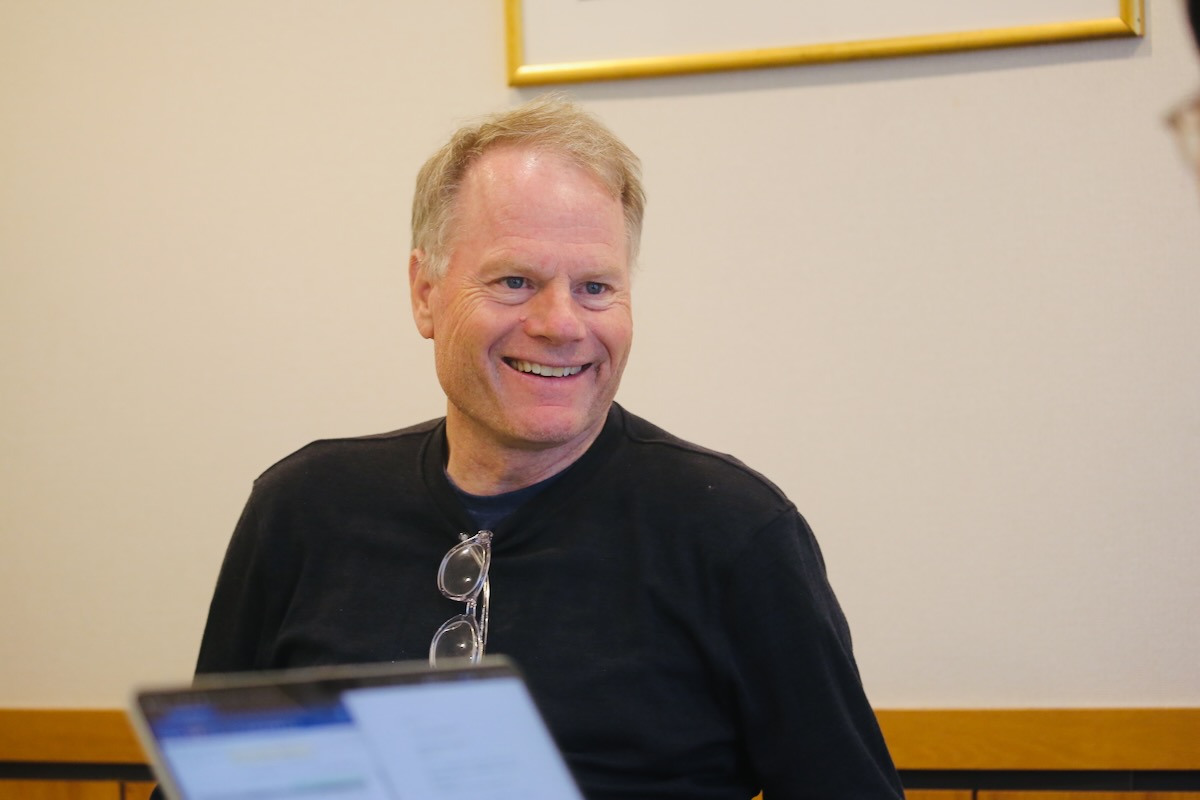
──初めて日本に来たのはいつ頃ですか?
ジョン・バークCEO:CEOになる以前の、1988年のことだったと思います。当時は国際営業とマーケティングを担当しており、同年にスイスでヨーロッパ初の支店を立ち上げました。その後イギリス、そしてドイツへと拡大させ、そこで得た自信と共に日本市場にやってきました。
──バブルの絶頂期だった当時の日本はどのような感じでしたか。

──進出する上で、どんな障壁がありましたか。
特に言語の壁は高かったですね。でもそれはドイツやオランダでも直面したこと。それよりも当時はライバルがまだ少なかったので、僕らにはアドバンテージがありました。何よりも日本は美しい風景など自転車に適した国で、当時の日本には自転車に興味のある人たちがたくさんいました。
──内需だけでビジネスが回るアメリカを飛び出し、ヨーロッパや日本に進出したのはなぜですか。
私は小さい頃から歴史に興味があり、大きなビジョンによって偉業を達成する話が好きだったからです。それにトヨタやBMW、アップルをはじめ、素晴らしい企業はインターナショナルなマーケットを相手にしています。世界が一つになっていくなかで、トレックをグローバルなステージへと押し上げたかったのです。
パンデミックが生み出した好機
──CEOに就任してからいくつもの苦難があったと思いますが、近年ではコロナ禍などがありました。
パンデミックは、私がCEOとして体験した中でも、特に大きな試練の一つでした。2020年4月にコロナウイルスが世界を襲い、空輸や船便が止まり、物流が完全にシャットダウンしました。これは未曾有の大惨事となると思いました。しかし3週間が経ち、人々は屋外でのエクササイズを求め、自転車店には外にまで続く長蛇の列が並んでいました。
3週間の危機が、その後2年間に及ぶ自転車ブームを作り出したのです。ビジネスという名の旅路には、山もあれば谷がつきものです。

トレック最大のライバルは?
──同じアメリカのスペシャライズドや、近年はドイツのキャニオンも年々勢いを増しています。CEOに就任して30年になろうかというトレックの歴史で、最大のライバルはどこですか。
それは時代によって常に変わり続けてきました。初期はシュウィンで、やがてトレックvsスペシャライズドという構図が生まれました。でも重要なのはいかにインターナショナルな企業である続けるか。ヨーロッパや日本、中国への進出を躊躇い、消えていったブランドは数多くありましたからね。
──これまで悔しいと感じた、他社のバイクはありますか。
悔しいという見方はしていません。でも「これは面白いアイディアだ」と思うことはあります。見つけたら「これを見てみてよ」とデザイナーに送ることも。でもそれはバイクに限らず、車やアップル製品、エルメスのブランケットの時もあります。
──ブランケットからも、ですか。
そう。インスピレーションはどこにでも転がっていますからね。



──自社で印象に残っているバイクはどれでしょう。
1992年に発売したトレック 5500ですね。トレック最初のカーボン製のバイクです。他社が「カーボンなんて酷い素材で、すぐ壊れてしまう」と言うなか、私たちはNASA出身の科学者などを含む素晴らしいチームを作り、カーボンバイクのリーディングカンパニーとなりました。
他には1995年に発売したYバイクやカーボンのマウンテンバイク。Fuel EXや2008年のマドンなども大好きなバイクです。それに最新のマドンGen 8も胸を張って良いバイクだと言えますね。
「心から愛せるプロダクトか?」
──プロダクトの開発にはいま、どの程度関わってらっしゃるのですか。
私はエンジニアではありません。ですが、素晴らしい製品だと判断することはできます。チームが開発したプロダクトを隔週で確認し、自分に「これは心から愛せるプロダクトか?」と問いかけます。つまり私がトレックの最終関門なのです。
その際はチームに1つだけではなく、複数のデザイン候補を求めます。その方がクリエイティビティを生むからです。最悪なのは1つのデザインと結婚(固執)することですからね。

──マドンなどトレックのロードバイク開発には、男女ワールドチームであるリドル・トレックの選手たちのフィードバックが強く反映されていると思います。他ブランドのようにチームへ機材提供するのではなく、タイトルスポンサーになるメリットはどこにありますか。
良い質問ですね。自社でチームを所有しなければ、選手たちに本当の意味で機材をテストしてもらうことは難しいからです。我々は以前、それで大変な苦労をしました。選手たちと密にコミュニケーションを取ることで、初めて良いものを作ることができるのです。
例えばマッズ・ピーダスンがスプリントするラスト500mにおけるバイクの動きを、彼が言語化する様はまさにプロフェッショナルそのもの。トレックはエンジニアリングと真剣に向き合うため、真剣にバイクをテストする選手に、機材の限界を超える手伝いをしてもらっているのです。
──それは女子チームも同じですか。
そうです。我々は(2019年)に妊娠したエリザベス・ダイグナンと契約を結びました。妊娠したことによって前チームとの契約が打ち切られた彼女を中心に、チームを立ち上げました。劣悪な環境だった女子ロードレース界を変えるために。そして彼女は2021年にパリ〜ルーベ・ファムの初代優勝者となりました。その時の彼女の写真は、いまも会社に飾ってあります。

──女性用のサイズの小さなバイクの開発、調整は大変でしたか。
そうですね。細部までこだわると大変です。しかし我々は女子チームでのテストを通してそれを実現させ、あらゆるライダーにとって機能する製品をつくり続けようと励んでいます。
──本日はありがとうございました。明日は富士ヒルに参加されると聞きました。
いままでクレイジーな自転車イベントに参加してきましたが、9,000人以上のライダーが24kmの登り坂に挑む、こんなイベントは初めてです。素晴らしい体験になるに決まっています。

──軽量になったマドンでも、十分登れることを証明するために?
もちろんです。マドンは我々が開発した最高のオールラウンドバイクです。スプリントはもちろん、クラシックレースから登りまで対応できます。それは(リドル・トレックのクライマーである)チッコーネがレースで示している通り。クライミングバイクとしても素晴らしい性能を発揮することでしょう。
──最後に抽象的な質問にはなってしまいますが、トレックは今後、日本でどうなっていくのでしょうか。
我々のミッションはどの国であっても変わりません。素晴らしい製品を作り、ホスピタリティと共に届ける。そしてより多くの人々に自転車に乗ってもらいたい。私は日本が大好きです。人々は礼儀正しく、街は綺麗で管理が行き届いている。もしかしたら日本人ではない私たちの方が、この国がいかにスペシャルであるかを、より実感しているのかもしれません。

text:Sotaro.Arakawa
photo:So Isobe
Amazon.co.jp
セガフレード・ザネッティ デカ クレム カフェポッド 18袋 (カフェインレスコーヒー)
Segafredo Zanetti
Segafredo Zanetti (セガフレード・ザネッティ) インスタント エスプレッソ 1.6g×10P
Segafredo Zanetti