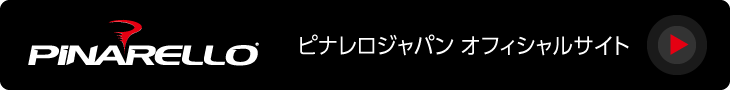ピナレロ DOGMA K10 photo:MakotoAYANO/cyclowired.jp
ピナレロ DOGMA K10 photo:MakotoAYANO/cyclowired.jpDOGMAの名を冠するもう一つのラインアップ、それがこの章で紹介するK10シリーズだ。ピュアレーシングバイクの頂点たるF10シリーズの走行性能をそのままに、より高いバーティカルコンプライアンス(縦方向の柔軟性)を与えられ、極上のエンデュランスレーサーとして仕上げられたシリーズだ。
プロにとっては「北のクラシック」で過酷な石畳を制するため、ホビーライダーにとっては身体へのダメージを抑えつつより速く遠くまで走る欧州のグランフォンドイベントをターゲットとして生み出されたKシリーズの歴史は、2011年に登場したKOBH60.1まで遡る。チームスカイから受けた、北のクラシック専用のDOGMAのSUVバージョンを、というリクエストに応える形で開発されたエンデュランスシリーズは幾度かのモデルチェンジを経て、今代のK10シリーズへと至った。
基本的な形状はF10シリーズと共通とされている。F10と同じ”T1100G Nanoalloy"で作られる各チューブにはカムテール形状の”Flatback”を採用するほか、TTバイクであるBOLIDE譲りの”Concave Down Tube”、フォーク先端の”フォークフラップ”などF10のエッセンスはそのままに、縦方向への柔軟性を向上させる設計が随所に導入されている。
 シートステイもスリムになり振動吸収性に寄与する
シートステイもスリムになり振動吸収性に寄与する 見た目にもF10と大きく異なるのはフレームの後ろ半分、チェーンステイとシートステイの形状だ。緩やかなS字を描くF10シリーズのシートステイと異なり、カーブを一か所減らしつつ曲率を大きくしたデザインとされ、チューブ自体も心持ちスリムになることで、縦方向への変形量をコントロール。一方、”FLEXSTAYS”と名付けられたチェーンステイは横方向に大きく潰され、横方向へのねじれ、つまりペダリングによって加わる変形に対しては強い一方で、路面からの入力に対してはしなやかに追従するデザインとなっている。
これらの設計によってリアトライアングル全体に高い柔軟性を持たせつつ、ペダリングパワーはロスせずに地面へと伝える優れた駆動効率を獲得。また、リラックスポジションを可能にする長めのヘッドチューブや、ホイールベースの延長による直進安定性の向上など、ジオメトリー全体をエンデュランス寄りに調整することで、総合的に身体へのストレスを軽減しているのがK10シリーズだ。
 ピナレロ DOGMA K10-S
ピナレロ DOGMA K10-S ピナレロの理想的なエンデュランスマシンとして送り出されているK10シリーズには2車種がラインアップされる。一つはノーマルなブレーキキャリパーを採用し、オリジナルモデルといえるDOGMA K10。そして、もう一つがシートステイ接合部にサスペンションを設置し、ソフトテールバイクとなったDOGMA K10-Sだ。
K10-Sは、先代のK8-Sにてデビューした軽量サスペンションシステム「DSS 1.0(Dogma Suspension System)」をさらに発展改良した電子制御サスペンション「eDSS 2.0(Electronic Dogma Suspension System)」を搭載する最先端のレーシングエンデュランス。
eDSS 2.0とは、サスペンションそのものだけでなく、シートチューブに内装される「コントロールセンサーシステム」やダウンチューブに内蔵される操作盤「ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)」からなる電子制御システムすべてを指している。
 K10-Sのアイコンでもあるリアサスペンション ストローク量は10mm程度
K10-Sのアイコンでもあるリアサスペンション ストローク量は10mm程度  K10-Sはディスクブレーキ仕様となる
K10-Sはディスクブレーキ仕様となる  サスペンションの状態を示すインジケーターLEDが装備されるHMI
サスペンションの状態を示すインジケーターLEDが装備されるHMI ジャイロスコープと加速度センサーから得た情報によってコントロールセンサーシステムが路面状況を識別し、サスペンションの状態を瞬時に切り替えることで、あらゆる路面状況において自動的に最適なセッティングを実現するeDSS 2.0。また、HMIは物理スイッチを備えており、手動によるサスペンションのセッティングを変更できるほか、BluetoothやANT+といった通信規格に対応することで、ガーミンやスマホによる操作も可能としている。
eDSS 2.0とK10シリーズのアイコンでもあるFLEXSTAYSによって、K10-Sのリアトライアングルは縦方向へ最大10mmという驚異的な変形量を獲得。路面からの衝撃を積極的にいなし、ライダーへの負担を極限まで減らすことに成功した。一方で、平滑な路面では自動的にサスペンションをロックすることでF10譲りの高い反応性を損なわない、究極のエンデュランスレーサーとして君臨する。
フレーム設計の妙により、軽さと反応性、快適性という相反する要素を高次元でバランスさせたK10、そして電子制御という先進的かつ意欲的なテクノロジーを投入し、ロードレースの世界にサスペンションの存在意義を確立しようというK10-S。ピナレロの誇るエンデュランスシリーズの持つ実力に迫るインプレッションをお届けしよう。
最強のエンデュランスレーサー DOGMA K10乗り比べ
 ピナレロの送り出す最高のエンデュランスバイク K10シリーズ 2モデルの違いに迫る
ピナレロの送り出す最高のエンデュランスバイク K10シリーズ 2モデルの違いに迫る ラグジュアリーかつレーシング 二律背反を剋したDOGMA K10
小西:エンデュランスモデルでもDOGMAの良さは健在です。ノーマルのK10はF10の反応性や軽快感を受け継ぎつつ、スタビリティが向上しているなというのが第一印象。どれくらいの安定感があるのかといえば、まだスポーツバイクに乗り始めたばかりの方でも、安心してボトルに手を伸ばせるような、そんなフィーリングですね。かといって、決して重さは感じさせないし、動き自体は機敏そのもの。大好きです。上萩:自分もかなり好印象でしたよ。特に下りの安心感は大きいですよね。テストコースに出てくる少し路面が荒れているダウンヒル区間でも、タイヤが地面に吸い付いているような感覚で、グリップ性能が上がったかのよう。FLEXSTAYSの効果なのでしょう、とにかく路面への追従性が高いし、乗り心地もとてもラグジュアリー。
 「タイヤを23cから25cに履き替えるくらい接地感が向上する」小西裕介(なるしまフレンド)
「タイヤを23cから25cに履き替えるくらい接地感が向上する」小西裕介(なるしまフレンド) 小西:快適性は高い一方で、剛性感はしっかりと出ています。本気でもがいても力が逃げている感覚は皆無ですし、レースでももちろん問題ないどころか、アドバンテージになるでしょう。正直、F10とK10どちらを選んでも間違いはないです。ただ、やはりK10の方が長い距離に向いていますので、自分がどういった距離のレースを目標とするかで選ぶといいかもしれません。周回コースならF10、ラインレースならK10が向いているのではないでしょうか。
 「荒れた路面への追従性はバツグン」小西裕介(なるしまフレンド) あとは長距離のツーリングだと断然K10ですね。ショップのイベントで立川から蓼科まで200km弱を走るイベントを毎年開催しているのですが、そういったライドではK10の持つ特性をフルに発揮することが出来るでしょう。
「荒れた路面への追従性はバツグン」小西裕介(なるしまフレンド) あとは長距離のツーリングだと断然K10ですね。ショップのイベントで立川から蓼科まで200km弱を走るイベントを毎年開催しているのですが、そういったライドではK10の持つ特性をフルに発揮することが出来るでしょう。上萩:いわゆる本場のグランフォンド的な走り方にぴったりフィットするバイクですよね。日本でもそういった乗り方をする人が多いはずで、実際にとても良い選択肢になるはずなのですが、どうしてもみんなF10シリーズに目が行っちゃう(笑)やっぱりピュアレーサーに惹かれちゃうんですよね。でも、実際の需要にマッチするのはK10なんじゃないかな、本当にいいバイクですよ。安心感があるのに、レーシングバイクと遜色のない走りをするんですから。なんなら、F10 DiskよりもK10の方がレーシングバイクらしさは強いと感じるほど、キレ味のある走りが身上です。
 「路面が荒れているダウンヒル区間でも安定している」上萩泰司(カミハギサイクル)
「路面が荒れているダウンヒル区間でも安定している」上萩泰司(カミハギサイクル)  「エンデュランスバイクだからと食わず嫌いしてたら勿体ない一台」上萩泰司(カミハギサイクル)
「エンデュランスバイクだからと食わず嫌いしてたら勿体ない一台」上萩泰司(カミハギサイクル)  「エンデュランスを銘打っているけれど、レースでも全然使えます」「タイヤを23cから25cに履き替えるくらい接地感が向上する」小西裕介(なるしまフレンド)
「エンデュランスを銘打っているけれど、レースでも全然使えます」「タイヤを23cから25cに履き替えるくらい接地感が向上する」小西裕介(なるしまフレンド) 小西:やっぱりFLEXSTAYSが働いているのはとてもよくわかりますよ、タイヤが跳ねちゃうようなところを走ると明白ですね。タイヤを23cから25cに履き替えた時に感じたのと同じくらいの違いがあります。だから登りでダンシングしてもトラクションが抜けづらいですし、座って淡々とリズムでこなしても良く進みます。
これからロードバイクを始める人でも、経済的に余裕があって、とにかくいいものが欲しいという方がいれば、ぜひこういったバイクに乗っていただきたいですね。自転車を長く楽しめるようになるはずです。
先進の電子制御ソフトテール DOGMA K10-S
小西:今回一番の目玉バイクですが、面白いですね、eDSS。僕は好きですよ、こういうの。ただ値段がかなり強気ですが(笑)上萩:正直、どれほどのものなんだ?と思って、いろいろ試してみたんですよ。特に一番のウリだろうオートマチックモードの判断がどれほど正確なのか、というのが気になって。凸凹したところを何度も行ったり来たりしてみたんですけど、思ってた以上に的確にモードを切り替えてくれるんです、きっと自分が手動でやっても同じくらいのタイミングになるだろうな、というくらいの絶妙さです。
 「オートマチックモードの切り替えが思った以上に正確で驚いた」上萩泰司(カミハギサイクル)
「オートマチックモードの切り替えが思った以上に正確で驚いた」上萩泰司(カミハギサイクル) 小西:私も切り替わりのスムーズさに驚きました。もっとタイムラグがあることを覚悟していたのですが、非常に自然でしたね。一回段差を降りただけでは反応せず、それが2~3秒以上続くようなところで切り替わるイメージですね。しっかりと路面の状況変化をとらえていると感じました。ガーミンの表示やLEDの色でモードの切り替わりを確認することもできますが、自転車が振動によって発するカタカタという音が明らかに変わりましたね。
スピード域によっても作動閾値が変わるようで、ゆっくり走っているとちょっとした段差では切り替わらないけれど、高速域になるとしっかりと作動するようです。決して楽をするためではなく、あくまで荒れた路面がたくさん登場するレースを速く走り抜けるための武器として開発されたシステムなのでしょう。
上萩:そうですね、パリ~ルーベに代表されるようなパヴェ系のレースでは非常に大きなアドバンテージになることは間違いないですよ。プロにとっても実用レベルの仕上がりでしょう。
 「駆動力をロスさせないトラクション性能の向上を第一にしています」小西裕介(なるしまフレンド)
「駆動力をロスさせないトラクション性能の向上を第一にしています」小西裕介(なるしまフレンド)  Kシリーズで唯一ディスクブレーキを装備するK10-S
Kシリーズで唯一ディスクブレーキを装備するK10-S  K10とK10-S、シートステイの形状が微妙に異なる
K10とK10-S、シートステイの形状が微妙に異なる 小西:特に登りで路面が荒れていると、ダンシング時にトラクションが抜ける経験というのは誰もが味わったことがあると思います。せっかく頑張って踏んでも、前に進まないようなシチュエーションですよね。でも、このK10-Sならそんな時でもしっかりとタイヤを地面に接地させて、推進力を伝えてくれます。速く走るためのトラクションコントロール機構としてのサスペンションですね。個人的にはこういう発想はとても大好き。
ロード用サスペンションといえば、昨年スペシャライズドが発表したRoubaixはフロントが稼働することで、ライダーへのダメージを抑えることを主眼にしたのに対して、K10-Sはリアでストロークも10mm程度に抑え、駆動力をロスさせないトラクション性能の向上を第一にしている。電子制御システムも、路面状況に合わせて最大の駆動効率を引き出すためのものですから、似て非なるバイクですよ。
 「あくまで速く走るためのサスペンション」小西裕介(なるしまフレンド)
「あくまで速く走るためのサスペンション」小西裕介(なるしまフレンド) 上萩:ある意味アメリカンブランドっぽい発想だよね。こちらもスペシャライズドになるけれど、彼らがMTBで採用するブレインショックも目的とするところは同じ。あちらは慣性バルブによる減衰コントロールシステムで、こっちは電子制御という違いはあるけれど、自動でサスペンションの動きをコントロールしようというゴールは一緒。そういったアクションをヨーロッパブランドであるピナレロが真っ先にロードバイクの世界に持ち込んできたのは面白いですよ。
面白いといえば、スポーツバイクの未来の形を感じさせてくれるバイクでもあるな、と。今ってIoTなんていって、家電をはじめいろんなものがインターネットにつながってコントロールされていく時代がすぐそこにやってきているわけじゃないですか。これはネットワークにつながっているわけじゃないけれど、こういった電子的な部品が自転車にも増えていけば、将来スポーツバイクの世界もどんどん変わっていくのかなと。
F10とK10 5モデルに乗って見えてきたDOGMAらしさとは?
 2人にとってもeDSSは注目の存在だったようだ。「スポーツバイクの未来の形を感じさせてくれる」上萩泰司(カミハギサイクル)
2人にとってもeDSSは注目の存在だったようだ。「スポーツバイクの未来の形を感じさせてくれる」上萩泰司(カミハギサイクル) 小西:今回5つのDOGMAに乗ったわけですが、どのバイクにも共通していたのが挙動の掴みやすさ。一貫性のある乗り味といいますか、どんな出力、どんなトルクのかけ方をしても、バイクの反応の方向性が変わらない。軽いギアで回したら進まないけど、重いギアを掛けると良く進む、あるいはその逆だったりするようなバイクって、実はかなり多いですが、DOGMAはそういったクセが少ないですね。
また、昔だとどっしりした安定感のある乗り味というのもDOGMAシリーズの持つ美点でしたが、最近はそこに加えて軽やかさも併せ持つようになっています。自然に前へ進んでいく直進性の高さと、ハンドリングや反応の軽さという相反する要素を併せ持つスーパーバイクとして、現在のDOGMAは完成していますね。
上萩:私が思うDOGMAらしさといえば、ハンドリングの良さ、安心感につながるヘッド周りの剛性感、踏んだ力をしっかり受け止めるBB周辺の剛性感、そしてラグジュアリーな乗り心地といった要素はどのバイクでも感じ取ることができました。どんな乗り方をしてもフレームはねじれることなくしっかりと前へ前へと走ってくれる。そんな、しっかりと芯が通った乗り味がDOGMAのエッセンスなのではないでしょうか。
ピナレロ DOGMA K10
| サイズ | 44、46.5、50、51.5、53、54、55、56、57.5、59.5 |
| カラー | 701/ホワイトオレンジ、702/ブラックレッド、703/BOB |
| 価格 | 680,000円(税抜、スタンダードカラー)、760,000円(税抜、MY WAYカラー) |
ピナレロ DOGMA K10-S
| サイズ | 44、46.5、50、51.5、53、54、55、56、57.5、59.5 |
| カラー | 968/ホワイトオレンジ、699/ブラックレッド、700/BOB |
| 価格 | 990,000円(税抜、eDSSサスペンション仕様 スタンダードカラー) 1,070,000円(税抜、eDSSサスペンション仕様 MY WAYカラー) 780,000円(税抜、DSSサスペンション仕様 スタンダードカラー) 860,000円(税抜、DSSサスペンション仕様 MY WAYカラー) |
※全て2018年2月1日からの新価格表記
提供:ピナレロジャパン 制作:シクロワイアード編集部